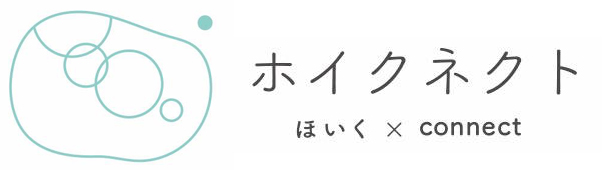誰かがやってくれているはずという無意識の怖さ
また、保育の現場で悲しい事故が起こりました。
詳細がわかってくるほど、「なぜ?」という思いが込み上げてきます。
そして記者会見を見て、つい感情的になる自分を抑えられなくなります。
大人たちの不誠実な対応で、突然失ってしまった大切な命。
御家族や御親族の方々のお気持ちはいかばかりかとお察し申し上げます。
心より慎んでお悔やみ申し上げます。
違和感のもとにあったもの
この事故に関して、違和感を感じた点はいろいろありますが、
その中でも特に強く感じたことは、
「違和感を感じない、またはそのままにしてしまうことが当たり前になっている」
そんな職員の意識でした。
低年齢の子どもたちを預かる施設の中では、
注意深く子どもたちを見守っていても、職員間で連携を取り合っていても、
怪我をさせてしまうことがあります。
そのため園内外の環境や、子どもたちの発達、過去の事例などから、
起こりやすい怪我や事故を洗い出し、
危険や事故に対して可能な限り事前に予測して予防をする、
リスクマネジメントを行なっています。
さらに潜在的な危険性を、事前に除去や回避できるようにしているのです。
その中で、職員一人ひとりの見守る位置や意識、連携など何度も話し合いをして
確認が行われる。それが本来の保育の現場の在り方だと思いますが、
今回の件では、その意識の薄さを感じたのです。
「自分がやらなくても、誰かがやってくれるはず」
「そんな大きい事故は、うちでは起こらないはず」
そんなふうに考えることが習慣になり、通常になっていくと、
危険を察知する感覚が意識の中に潜り込んで、
無意識、無自覚になり、気づく力が失われる怖さがあると思っています。
「おかしい」と思ったことを誰かに伝えて共有したり、
人は違うと言っても、自分で確かめてみたり、
何より、「誰かが」ではなく、
自分が子どもたちに対しての責任があるという意識を持つ、
そんな風土があったのだろうか・・・
そう思わずにはいられませんでした。
絶対はない
あってはならないことではありますが、
自分のいる園でも、もしかしたら起こり得ること
そんな意識をおそらくどの園でも感じたのではないでしょうか。
保育士も疲れてくると判断が鈍ることもありますし、つい今までそこにいたのに、
子どもの動きに応じて移動したら怪我をしていた。ということもあります。
また新年度が始まった時など、子どもたちがまだ落ち着かない時期や、
職員の誰かが休んでいて、いつもと違う体制だったという時、
そんな状況は保育の中では日常茶飯事です。
その時はできたけれど、ずっとできるとは限りません。
けれど、
職員間のやりとりが当たり前にできている関係性があり、
年齢や経験に関係なく、気づきを伝えることや受け入れること、
つまり対話をする風土があれば、リスクマネジメントに繋がります。
一人ひとりの意識とともに、組織の風土は組織力になるのだと感じています。
命に対して、驕らず
誰か、ではなく自分の頭と心で考えて
専門職としての意識を再確認していきましょう。
これは、現場にいる方々だけに伝えているのではなく、
現場を離れていても、保育士として生きている自分自身にも
自戒の念を込めて胸に刻んでいこうと思います。